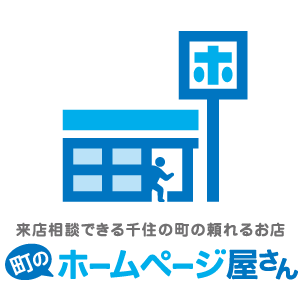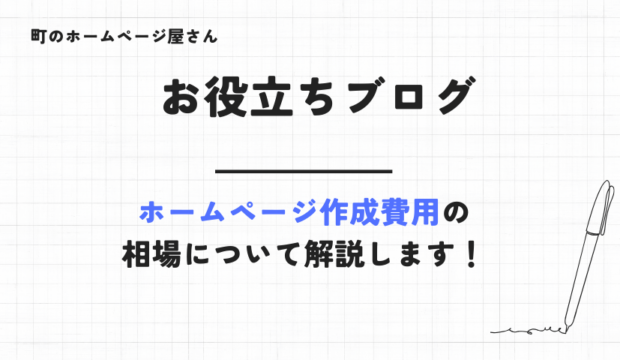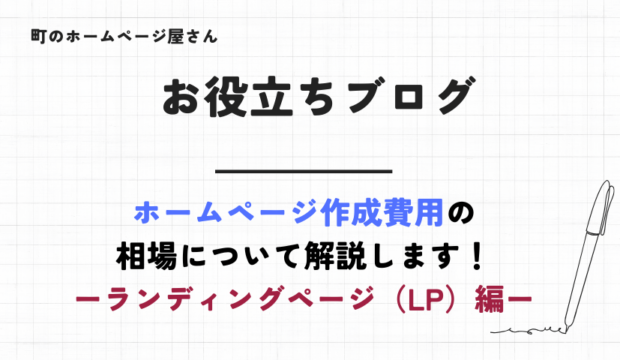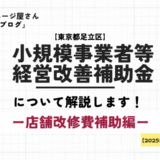「ホームページを作りたいけど、いったいいくらかかるの?」
いざ制作を検討し始めると、費用の目安が見えず、戸惑う方も多いのではないでしょうか。
インターネットで調べてみても、10万円〜数百万円と幅が広く、「結局うちの場合はどれくらい?」と悩んでしまう方も少なくありません。
これは、ホームページの目的や内容、依頼先、仕様、運用方針などによって費用が大きく変動するためです。
本記事では、企業・個人を問わず、これからホームページを制作しようとしている方が「自分に合った費用感」をつかめるよう、制作費用の相場や考え方を項目別にわかりやすく解説します。
ホームページ製作の費用と相場を徹底解説!ーもくじー
-
- ホームページ制作費用の相場を理解する
1-1 ホームページ制作費用の一般的な相場
1-2 企業向けと個人向けの相場の違い - ホームページ制作の目的とその影響
2-1 ホームページを制作する目的とは
2-2 目的別の費用相場の違い
- ホームページ制作の仕様が費用に与える影響
3-1 デザイン性と機能が費用に与える影響
3-2 完全オリジナルとCMSでの制作相場 -
依頼先によるホームページ制作費用の違い
4-1 制作会社に依頼した場合の相場
4-2 フリーランスに依頼した場合の相場
4-3 依頼先で変わる作成費用の具体例 - ホームページ制作の料金内訳
5-1 制作費用に含まれる主な項目
5-2 運用保守費用の相場とその重要性 -
高額と低額なホームページ制作の違い
6-1 高額な制作の特徴とメリット
6-2 低額な制作のリスクと注意点
- 費用を抑えるためのポイント
7-1 費用を抑えるための具体的なコツ
7-2 相見積もりの重要性とその方法 - ホームページ制作の流れと工程
8-1 ホームページ制作の一般的な流れ
8-2 各工程にかかる費用の目安 - ホームページ制作に関するよくある質問
9-1 自作と外注の比較
9-2 ホームページ制作のメリット・デメリット - さいごに…
- ホームページ制作費用の相場を理解する
1.ホームページ制作費用の相場
この章では「ホームページ制作費用の相場を理解する」について解説します。
具体的には、ホームページ制作費用の一般的な相場、企業向けと個人向けの相場の違いといった内容を順にご紹介します。
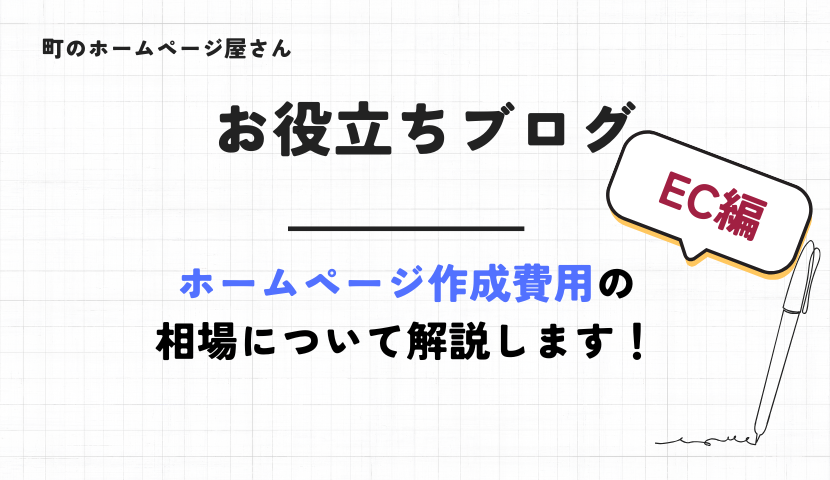
2024.11.08
ECサイトを作成しようとした時、その費用を調べると、サイトによって価格が大きく異なりますよね。 これは、依頼先やサイトの規模、目的によって作業内容が異なるため、費用にも差が出るからです。 「何によって相場が変わるの?」「どうすれば費用を抑えられる?」などなど、ECサイトの作成費用の概要をご案内し...
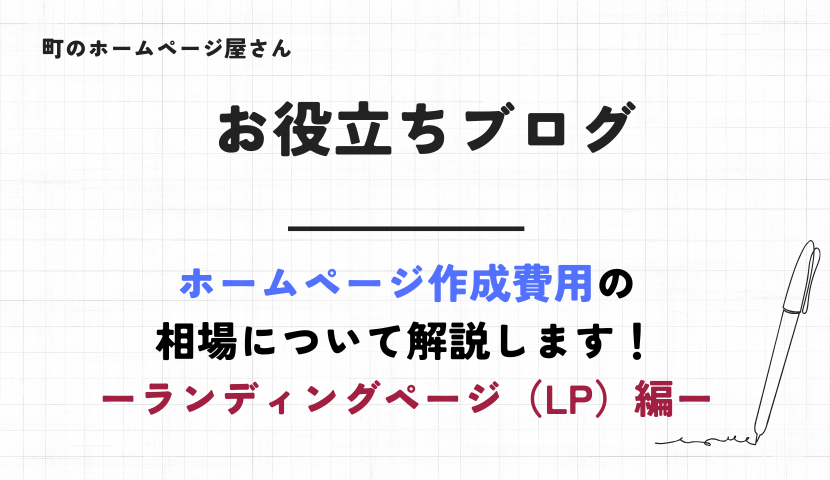
2024.11.01
ホームページを制作しようとした時、その費用を調べると、サイトによって価格が大きく異なりますよね。 これは、依頼先やサイトの規模、目的によって作業内容が異なるため、費用にも差が出るからです。 「何によって相場が変わるの?」「どうすれば費用を抑えられる?」などなど、ホームページの作成費用の概要をご案...
【1-1】 ホームページ制作費用の一般的な相場とは?
ホームページを作成するうえで、誰もが最初に気になるのが「いくらかかるのか?」という制作費用の問題です。
実際のところ、ホームページの制作費用には明確な“定価”があるわけではなく、さまざまな要因で大きく変わるのが現実です。
ここでは、制作費用が変動する主な要素として 「ページ数と機能」「依頼先の違い」「保守・運用費」 の3つに分けて、相場感と注意点を解説します。
1. ページ数と機能によって費用は大きく変動
制作費用を大きく左右するのが、ホームページに必要なページ数と機能の複雑さです。
たとえば、会社概要・サービス紹介・お問い合わせフォームといった基本的な構成の5ページ程度のコーポレートサイトであれば、10万〜30万円程度で制作可能なケースもあります。
一方で、CMS(WordPress等)を使って更新性を高めたり、予約機能・会員制コンテンツ・EC機能などを追加したりすると、開発工数も増え、50万〜200万円以上かかることも珍しくありません。
2. 依頼先によって価格に差が出る
同じような内容のホームページでも、どこに依頼するかによって価格が大きく異なります。
-
フリーランスに依頼する場合:比較的安価(10万円〜)で対応してくれることが多いですが、デザインやサポート面では個人のスキルに左右されます。
-
制作会社に依頼する場合:ヒアリングから設計、デザイン、開発まで一括で任せられる反面、費用は50万円〜数百万円になることも。
-
クラウドソーシング・テンプレートサービスを活用する:初期費用を抑えたい方には、無料〜数万円で制作可能なサービスもありますが、オリジナリティには限界があります。
⇒複数社から見積もりを取得して比較検討することが、費用面でも品質面でも失敗しないコツです。
3. 初期費用だけでなく「保守・運用費用」も見逃さずに
ホームページは「作って終わり」ではありません。意外と見落としがちなのが、ホームページ完成後にかかる継続的な費用です。
代表的なものは以下の通りです。
継続的な費用サーバー代(月額1,000〜3,000円)
ドメイン代(年額1,000〜3,000円)
SSL証明書代(無料〜年額数万円)
保守・管理費(セキュリティ対応やバックアップなど)
→ 外部に任せる場合は月額5,000円〜1万円程度が相場
とくにビジネス用のサイトであれば、セキュリティやトラブル対応のためにも、保守契約を結んでおくことをおすすめします。
予算が限られている場合は、無料テンプレートやCMS(WordPress)を活用するのもひとつの手段です。
また、「まずは簡易的なページを作って、後から拡張する」という段階的な進め方も現実的な方法です。
ホームページ制作費用は、内容や依頼先、運用体制によって大きく変わります。大切なのは「目的に応じた費用感を把握し、無理のない形で制作を進めること」です。
最初に全体像を理解しておくことで、想定外の出費を避け、効果的なホームページを作る第一歩になります。
【1-2】 企業向けと個人向けの相場の違い
ホームページ制作の相場は、「誰のために、どんな目的で作るか」によって大きく変わります。
特に、企業や事業者向けと個人向けでは、必要な内容・機能・役割が異なるため、制作費用にも明確な差が生じます。ここでは、一般的な違いを3つの視点からご案内します。
1. 企業の規模や目的で費用は変動する
企業向けのホームページは、制作する内容がより戦略的・組織的である傾向にあります。特に中堅〜大手企業では、会社のブランドイメージや信頼性を高めるためのコーポレートサイトとして、デザイン性やマーケティング機能を重視した構成が求められます。
たとえば、以下のような機能が加わることも珍しくありません。
-
会員管理や予約システム
-
採用ページやIR情報の掲載
-
多言語対応やセキュリティ機能
このような仕様により、制作費用は100万円以上かかるケースもあります。
一方、中小企業やスタートアップ、地域ビジネスなどでは、情報発信を目的としたシンプルな構成で済むことも多く、20万円〜50万円前後の範囲に収まるのが一般的です。
2. 個人や小規模事業者は比較的低価格に
個人事業主やフリーランス、副業での活動など、小規模なビジネスや個人利用のホームページでは、初期費用を抑えたいというニーズが強くなります。
このような場合、以下のような選択肢が検討されます。
-
テンプレートやノーコードツールの活用
-
CMS(例:WordPress)を使った自作
-
最低限のページ構成での発信型サイト(ブログ、ポートフォリオなど)
このようなサイトであれば、5万円〜15万円程度の制作費用で対応可能な場合もあります。
個人利用においては、マーケティングや専門的なSEO対策よりも、「自分の活動やサービスを紹介する」というシンプルな目的が中心となることが多く、全体の構成もコンパクトにまとまりやすくなります。
3. 必要な機能や目的が費用差を生む
企業と個人では、ホームページに求める役割やビジネス的な目的が異なるため、必要な機能や設計思想も変わります。
| 利用者 | 一般的な目的 | 主な機能例 |
|---|---|---|
| 企業(会社・法人) | 信頼性の向上、採用強化、顧客獲得 | お問い合わせフォーム、SEO対策、更新機能、セキュリティ対策 |
| 個人(個人事業主・副業) | 自己紹介、活動報告、軽い集客 | SNS連携、ポートフォリオ掲載、ブログ機能など |
企業向けの場合は、マーケティング視点での導線設計や、成果を上げるためのページ構成が重視されるため、その分制作コストにも反映されます。
2.ホームページ制作の目的とその影響
この章では「ホームページ制作の目的とその影響」について解説します。
具体的には、ホームページを制作する目的とは、目的別の費用相場の違いといった内容を順にご紹介します。
【2-1】 ホームページを制作する目的とは
ホームページは、単に情報を並べる場所ではありません。その役割や目的を明確にすることこそが、費用対効果の高いサイトを制作するための第一歩です。
目的が曖昧なまま進めてしまうと、見た目は整っていても、顧客の心をつかめず、成果につながらない「形だけのホームページ」になってしまいかねません。
ここでは、企業・団体がホームページを制作する主な目的として代表的な3つを紹介します。それぞれの目的に応じて、必要なコンテンツやトップページの構成、使用する機能やデザインの方向性が大きく異なるため、制作前の整理が重要です。
1. 企業・団体の“顔”としての信頼性向上
会社や団体の信頼性を高めることを目的とする場合、ホームページはその第一印象を決定づける「顔」になります。
とくに初めて訪れた人にとっては、そのトップページが企業の価値を判断する材料となるため、プロらしいデザインや情報の整理が重要です。
-
実績紹介や受賞歴
-
代表メッセージや理念
-
顧客の声・導入事例
-
メディア掲載情報
このような信頼を生むコンテンツを適切に配置することで、閲覧者に安心感を与えることができます。そのため、外観だけでなく、内容面でもプロフェッショナルであることが求められます。
2. 集客・売上増加を目的とするケース
商品やサービスの購入、資料請求、問い合わせといった具体的なアクションを増やしたい場合は、集客・売上向上を目的としたホームページが必要になります。
この目的のためには、検索エンジンで見つけてもらえるようなSEO対策が欠かせません。また、見込客が興味を持ってから行動に移るまでの流れを意識した導線設計やCTA(行動喚起)も重要です。
-
ターゲットに合ったコンテンツ設計
-
サービス紹介ページの強化
-
問い合わせフォームやチャット導入
-
スマホ対応や表示速度の最適化
これらを効果的に組み合わせることで、サイト全体の集客力とコンバージョン率が高まり、ビジネス成果にもつながります。
3. 採用活動の強化
近年では、求職者も会社選びの際にホームページをしっかりチェックするのが一般的です。
採用活動を強化したい場合には、企業の魅力を伝えるための専用コンテンツを充実させることが不可欠です。
-
社員インタビューや社内の雰囲気紹介
-
働き方や福利厚生の説明
-
応募のしやすい導線設計
-
採用専用ページの設置
こうした情報を見やすく整理し、ご覧いただいた求職者に「ここで働きたい」と思ってもらう設計が求められます。結果として、応募数の増加やミスマッチの減少にもつながるでしょう。
▶目的を明確にすることが成功の鍵
ホームページの制作においては、「誰に」「何を」「どう伝えるか」という目的の定義がすべての土台になります。
目的がはっきりしていれば、必要なコンテンツ、デザイン、機能、サーバー構成などの要件も明確になり、制作会社やプロの制作者とのやりとりもスムーズになります。
そのため、制作の初期段階で目的をきちんと整理し、共有することが、無駄な費用を防ぎ、効果的なサイトを作るための最重要ステップです。
【2-2】 目的別の費用相場の違い
ホームページ制作の費用相場は、何のためにホームページを作るのかという「目的」によって大きく異なります。
なぜなら、必要とされる機能・デザイン・コンテンツの内容が大きく異なり、それに伴い制作工程や作業量も変わるためです。
ここでは、代表的な3つの目的に分けて、それぞれの特徴と費用感をご案内します。
1.情報提供型ホームページの費用相場
企業の概要やサービス内容、所在地、連絡先などを掲載し、閲覧者に基本的な情報を提供することが目的のホームページです。
このタイプのサイトは、必要なページ数も比較的少なく、CMSを活用して効率的に構築されることが多いため、費用は比較的抑えられる傾向にあります。
-
一般的な費用相場:10万円〜40万円程度
-
主な利用者:中小企業、士業、店舗、団体など
-
主な構成:トップページ/会社案内/サービス紹介/アクセス/お問い合わせ など
多くの企業がまずはこのタイプから導入することが多く、初期段階のホームページとしても適しています。
2.集客・販売型ホームページの費用相場
商品・サービスの販売促進や見込み顧客の獲得を目的とするサイトです。
集客効果を高めるために、SEO対策やコンテンツマーケティング、フォーム最適化、広告運用連携などの機能や設計が求められます。
-
一般的な費用相場:50万円〜150万円程度
-
主な利用者:EC事業者、サービス業、コンサル業、BtoC向けビジネスなど
-
特徴:検索上位表示を狙うためのブログや記事ページ、LP、CTAの導線設計などを別途実装
このタイプのサイトは、売上や問い合わせといった明確な成果につなげるために多くの施策が必要となるため、制作費も高くなる理由があります。
3.ブランディング型ホームページの費用相場
企業イメージやブランド価値の向上を重視するサイトです。
視覚的な印象やストーリーテリングが重視され、高品質な写真・動画・デザイン・コピーライティングなど、専門的かつクリエイティブな要素が多く含まれます。
-
一般的な費用相場:100万円〜300万円以上
-
主な利用者:大手企業、ブランド戦略を強化したい事業者、採用に力を入れている企業など
-
特徴:ビジュアル重視の設計/独自の表現手法/映像・アニメーション活用/ブランドコンセプトの訴求
このタイプのサイトでは、ドメイン取得から構成企画、撮影・動画編集なども別途必要になることがあり、費用が大きくなりがちです。
費用の違いは「目的」によって生まれる
ホームページ制作費用に大きな違いが出る理由は、目的に応じて必要な要素が異なり、その分の手間と専門性が加わるからです。
同じ「5ページ構成のサイト」でも、掲載する情報、設計の深さ、成果へのつなげ方によって、数十万円以上の差が出ることも珍しくありません。
制作会社に見積もりを依頼する際には、目的をしっかりと伝えることが重要です。
「なぜそのサイトが必要か」「どのように活用したいのか」といった前提を共有することで、より正確な費用感が提示され、予算に合った提案を受けやすくなります。
3.ホームページ制作の仕様が費用に与える影響
この章では「ホームページ制作の仕様が費用に与える影響」について解説します。
具体的には、デザイン性と機能が費用に与える影響、完全オリジナルとCMSでの制作相場といった内容を順にご紹介します。

2025.07.24
ホームページは、ビジネスの信頼性や集客力を大きく左右する重要なツールです。 とはいえ、「できるだけ費用を抑えたい」と考える方も多いのではないでしょうか。 近年は、低価格ながらも高品質なサービスを提供する制作会社が増えており、賢く選べば十分に満足できるサイトを作ることが可能です。本記事では、格安ホ...
【3-1】 デザイン性と機能が費用に与える影響
ホームページ制作において、デザインや機能の仕様によって費用は大きく変わるものです。
単にページ数だけでなく、「どの程度デザインにこだわるか」「どのような機能を追加するか」といった要素によって、工数とコストが大きく左右されます。
以下では、特に費用に影響しやすい3つのポイントについてご紹介します。
1. デザインの複雑さとこだわりが費用を左右する
シンプルで情報を伝えるだけのレイアウトと、ブランディングに配慮したビジュアル重視のデザインでは、制作にかかる工数がまったく異なります。
たとえば、画像や配色、フォント構成まで細かく設計されたサイトや、アニメーションを多用した動きのあるページでは、デザインにかかる時間と専門的スキルが必要になり、その分費用も上がります。
また、商品やサービスのイメージを効果的に伝えるために、写真撮影や動画制作などの追加オプションを導入するケースもあり、これらは別途費用が発生します。
2. 実装する機能の数と難易度で費用が変動する
ホームページに求められる機能が増えるほど、費用は上昇します。
-
問い合わせフォームや予約システムの導入
-
会員登録・管理機能
-
商品検索機能やカート機能(ECサイト向け)
-
外部サービスとの連携(例:メール配信システム、CRMなど)
例として、これらの機能をどの程度導入するか、またその実装の難易度が高いかどうかが、見積額に大きく影響します。
また、セキュリティ強化やデータの保護設計を含むようなカスタム要件も、費用増加の主な要因となります。
3. レスポンシブ対応の有無も重要な費用要素
今や多くのユーザーがスマートフォンからホームページを閲覧しています。
そのため、PCだけでなくスマホやタブレットにも対応する「レスポンシブデザイン」が標準となりつつあります。
レスポンシブ対応を行う場合、画面サイズごとに最適なレイアウトやデザインを設計・調整する必要があるため、工数が増え、その分の費用が上乗せされます。
ただし、ユーザビリティの向上やSEO評価にもつながるため、費用対効果の高い投資といえるでしょう。
▶費用をコントロールするためには?
ホームページの制作費用を抑えるには、「すべてにこだわる」のではなく、必要なデザインや機能に優先順位をつけることが大切です。
-
初期段階では最低限の機能にとどめ、後から段階的に追加していく
-
汎用の機能を活用し、完全な独自開発を避ける
-
既存テンプレートのカスタマイズでイメージに近づける
などの工夫をすることで、予算内で効果的なサイト構築が可能になります。
【3-2】 完全オリジナルとCMSでの制作相場
ホームページ制作の費用は、どの制作手法を採用するかによっても大きく異なります。
特に「完全オリジナルで作るか」「CMS(コンテンツ管理システム)を活用するか」という選択は、予算・自由度・運用面に直接影響します。
それぞれの特徴と費用感を理解し、自社に合った方法を選ぶことが重要です。
1.完全オリジナルは自由度が高い分コストも高額に
完全オリジナルのホームページは、デザインや機能を一から構築するため、企業独自の世界観やブランディングを細部まで表現できるのが大きなメリットです。
例えば、独自開発の検索機能や複雑なフォームシステム、独特な動きのあるUIなども実装可能です。
しかしその分、デザイナー・エンジニア・コーダーそれぞれの工数が多く必要となり、制作費用は高くなる傾向があります。
▷相場の目安:80万〜300万円以上
▷想定されるケース:大企業のブランドサイト、採用サイト、ECサイトなど
「他社とまったく違う印象を与えたい」「競合との差別化を徹底したい」など、こだわりが強い場合に向いています。
2.CMSを活用すれば、テンプレート利用で費用を抑えられる
CMS(Content Management System)は、あらかじめ用意されたテンプレートや管理画面を利用して、効率的にホームページを構築・運用できるツールです。
中でも広く使われているのが「WordPress」で、多くの中小企業や個人事業主が利用しています。
CMSでは、テンプレートをベースにしたデザインや機能の構築が可能で、大きな開発コストをかけずに制作をスタートできる点が魅力です。
-
相場の目安:20万〜80万円程度
-
想定されるケース:情報提供型サイト、ブログ、スモールビジネスサイトなど
さらに、CMSなら専門知識がなくても自分で更新できるため、運用面でもコストを抑えやすいという利点があります。
3.カスタマイズの範囲で費用は上下する
CMSを導入しても、「カスタマイズの程度」によっては費用が高くなることもあります。
例として以下のようなケースでは、追加費用が発生します。CMSを利用するからといって、常に低コストに抑えられるわけではない点に注意が必要です。
-
テンプレートの構造を大きく変更する
-
標準機能では実装できない独自システムやフォームを追加する
-
セキュリティや表示速度を最適化する高度な対応を行う
▶最適な選択のためには「予算と目的のバランス」が重要
「完全オリジナル」か「CMS」かの判断は、予算・目的・運用体制のバランスを見極めることがカギになります。
-
予算が限られている → CMS + テンプレートでスタート
-
更新を自社で行いたい → WordPress導入を検討
-
ブランディングや特殊機能が最重要 → 完全オリジナルも視野に
また、CMSの導入やカスタマイズに強い制作会社を選ぶことで、無駄のない構成と最適な費用設計が可能になります。
4.ホームページ制作費用の依頼先による違い
この章では「依頼先によるホームページ制作費用の違い」について解説します。
具体的には、制作会社に依頼した場合の相場、フリーランスに依頼した場合の相場、依頼先で変わる作成費用の具体例といった内容を順にご紹介します。
【4-1】 制作会社に依頼した場合の相場
ホームページを制作会社に依頼する場合、その費用は会社の規模や実績、提供されるサービスの範囲によって大きく異なります。
一般的に、小規模な制作会社では数十万円程度から、大手企業やブランド戦略まで支援するような会社では100万円以上の費用が発生することも珍しくありません。
1.費用の内訳と対応範囲を事前に確認する
制作会社へ依頼する場合、企画・デザイン・構築・CMS導入・レスポンシブ対応などを一括で請け負ってくれることが多く、
一見すると価格は高めに感じるかもしれませんが、各工程が整理され、品質管理も安定しているという大きなメリットがあります。
また、必要に応じて以下のようなこともセットで提供している会社もあり、ワンストップでサイトを作ることが可能です。
-
写真・動画の撮影や編集
-
サーバーやドメインの取得代行
-
ロゴやバナーなどのデザイン制作
依頼前には、どの項目が見積もりに含まれているのかを詳細に確認することが大切です。
2.実績と相場の関係にも注目を
制作会社の実績や得意分野、過去に制作した業界の経験によっても、見積もり金額には差があります。
たとえば以下のように、自社の業種や目的に合った制作会社を選ぶことで、満足度の高いサイトを作ることができます。
そのためには、必ずポートフォリオ(制作実績)を確認し、自社と同じような規模・業種の事例があるかをチェックしましょう。
-
コーポレートサイトの構築経験が豊富な会社
-
飲食・美容・医療など業種に特化した会社
-
集客・マーケティングに強みをもつ会社
3.保守・運用費用も予算に含めておく
ホームページは「作って終わり」ではなく、更新・保守・セキュリティ対応など、運用にかかる費用も継続的に発生します。
制作会社によっては、月額の保守サービスを提供しているところもあり、その内容と料金体系はさまざまです。
-
サーバー保守・バックアップ対応
-
CMSやプラグインのアップデート
-
更新作業代行や問い合わせ対応 など
このようなサービスが必要な場合は、初期費用とあわせて運用費用も含めた総予算を立てることが大切です。
▶ポイントまとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制作費用の目安 | 30万円〜100万円以上(規模・内容により変動) |
| 含まれる作業 | 企画、デザイン、CMS構築、レスポンシブ対応 など |
| 注意点 | 見積もりの内訳を必ず確認し、実績やサポート体制もチェック |
| 保守費用 | 月額数千〜数万円。内容により大きく異なる |
▶制作会社に依頼する場合は、価格だけでなく、信頼性や対応力、提案力なども含めて総合的に判断することが、失敗しないホームページ制作のコツです。
【4-2】 フリーランスに依頼した場合の相場
ホームページ制作をフリーランスに依頼する場合、制作会社よりも料金を抑えられる傾向があります。
とはいえ、すべての案件が格安で対応できるわけではなく、依頼する内容やフリーランスのスキルレベルによって価格は大きく異なります。
ここでは、フリーランスへの依頼における相場と特徴について解説します。
1. 制作会社よりも費用を抑えやすい
フリーランスは個人で活動しているため、人件費や管理コストがかからず、価格を柔軟に調整できるというメリットがあります。
そのため、同じ内容でも制作会社に比べて費用を安く見積もってもらうことが可能です。
-
ランディングページ(1ページ完結型):3万〜10万円程度
-
小規模ホームページ(5〜10ページ程度):10万〜30万円前後
-
中規模サイトやカスタマイズを伴う制作:30万円以上になることも
ただし、デザイン・コーディング・CMS構築などすべてを一人でこなす必要があるため、内容によっては時間がかかる場合もあります。
あらかじめ、月額の運用サポートを希望する場合も、その対応可否や料金を確認しておきましょう。
2. 直接コミュニケーションを取りやすい
フリーランスに依頼する大きなメリットは、依頼者本人と直接やり取りができる点です。
制作会社では、ディレクターや営業担当を通すケースが一般的ですが、フリーランスであれば要望をダイレクトに伝えることが可能です。
修正や追加の依頼も、柔軟に対応してもらいやすいという利点があり、プロジェクトの進行もスムーズになることがあります。
その反面、スケジュールや納期についてはすべて自己管理に依存するため、時間のずれや進捗トラブルが起きる可能性もある点には注意が必要です。
契約前に、納期・修正回数・範囲・支払い方法などをしっかり取り決めておくことがトラブル防止につながります。
3. スキルや実績にばらつきがある
フリーランスは実務経験が豊富なプロもいれば、副業レベルの方までさまざまです。
そのため、料金が安いからといってすぐに依頼を決めるのではなく、ポートフォリオや実績を確認することが重要です。
注意すべき点・過去にどんなサイトを制作しているか(業種・ジャンル・デザイン性)
・使用しているツールやCMS(WordPressなど)の理解度
・依頼内容に似た実績があるかどうか
・クライアントのレビューや評価(クラウドソーシングサイト利用時)
▶「いくらでお願いできますか?」と検索や相談をする前に、制作内容と予算の目安を用意しておくと、スムーズに見積もりをもらうことができます。
フリーランス依頼のポイントまとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 費用相場 | 数万円〜30万円前後(規模・内容により変動) |
| メリット | 料金が安く、柔軟に対応してもらいやすい |
| デメリット | スキル差が大きく、品質や納期に注意が必要 |
| 契約時の注意点 | 制作範囲・納期・修正対応を事前に明文化すること |
フリーランスへの依頼は、コストを抑えつつ、柔軟な対応を求める個人事業主や中小企業にとって有効な選択肢です。
ただし、契約内容を明確にし、信頼できる相手かを慎重に見極めることが、納得のいくホームページ制作につながります。
5.ホームページ制作の料金内訳
この章では「ホームページ制作の料金内訳」について解説します。
具体的には、制作費用に含まれる主な項目、運用保守費用の相場とその重要性といった内容を順にご紹介します。
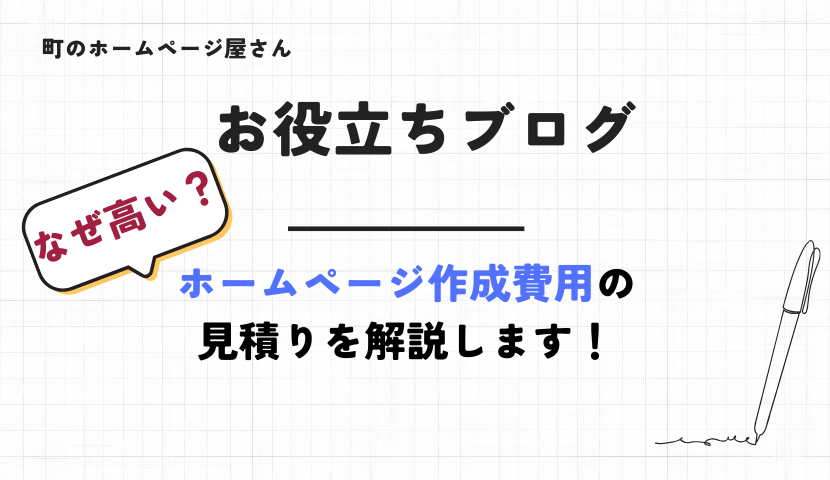
2024.11.06
ホームページを作成しようとその費用を調べると、「なぜこんなに高いんだろう…?」と思ったことありませんか? それは、ホームページ作成に多くのカスタマイズが必要であったり高い品質が求められ、専門的なスキルと時間がかかるため、結果として費用が高くなると考えられます。 「何によって相場が変わるの?」「ど...
【5-1】 制作費用に含まれる主な項目
ホームページ制作を依頼する際にまず確認しておきたいのが、制作費用に何が含まれているのかという点です。
同じ「制作費用」という言葉でも、その内容や範囲は依頼先によって異なるため、事前に詳細を把握しておくことが予算管理と費用対効果を高めるポイントになります。
ここでは、一般的なホームページ制作で発生する主な費用項目について解説します。
1.企画・構成費
ホームページは、ただ見た目を整えるだけでは意味がありません。目的やターゲット層に合わせた情報設計が必要です。
この段階で発生するのが「企画・構成費」です。
-
サイトの目的の明確化(例:集客、採用、ブランディング)
-
必要なページやコンテンツの洗い出し
-
ページ構成案(サイトマップ)の設計
-
ユーザー動線の検討
といった作業が含まれ、ここをおろそかにすると、途中での修正や機能追加が発生し、結果的に費用が膨らむことがあります。
費用の目安は数万円〜10万円前後が一般的です。
2.デザイン費
デザイン費は、サイトの第一印象やブランドイメージを決定づける重要な要素です。
ビジュアルの方向性を定め、トップページや下層ページのレイアウトを制作していくための費用で、以下のような作業が含まれます。
-
トップページ・下層ページのレイアウト作成
-
カラー・フォントなどのブランドガイドラインに基づく設計
-
写真・アイコンの選定や編集
企業のブランディングと連動させるようなデザインはこだわりが求められるため、費用も高くなる傾向があります。
目安としては、10万円〜30万円前後が一般的です。
3.コーディング費
デザインを実際にWeb上で閲覧できる形に仕上げるのがコーディングです。
HTMLやCSS、JavaScriptなどの言語を使い、静的なデザインを動きのあるページに変換していきます。
-
レスポンシブ対応(スマホ・タブレット最適化)
-
アニメーションの実装
-
フォームの設置
-
SEOを意識した構造設計(構造化データ、見出しの最適化 など)
といった技術的な作業が含まれ、制作後に集客や検索順位にも影響を及ぼす重要な工程です。
コーディング費は、ページ数や機能の複雑さに応じて変動しますが、10万円〜40万円程度が目安です。
その他、確認しておきたい制作費用の項目
上記3つに加えて、下記のような費用が含まれるかどうかを事前に確認しておくと安心です。
| 費用項目 | 内容 |
|---|---|
| 写真素材代 | 商用フリー素材の使用 or 撮影費用が別途発生する場合あり |
| 原稿作成 | テキストライティングを依頼するか、自社で用意するか |
| CMS導入費 | WordPressなどの管理システムを組み込む費用 |
| 公開作業 | サーバー環境へのアップロード、SSL対応など |
ホームページを適正な価格で制作するためには、制作費用の内訳を理解し、各工程が見積もりにどう反映されているかを比較することが重要です。
一見高く見える費用でも、戦略的な構成・デザイン・SEO対応が含まれていれば結果的に集客につながるケースもあります。
まずは自社の目的と予算を明確にし、必要な構成や工程を取捨選択しながら、費用対効果の高いホームページ制作を目指しましょう。
【5-2】 運用保守費用の相場とその重要性
ホームページは「公開して終わり」ではなく、継続的な運用と保守が必要不可欠です。
更新が止まったままのホームページや、セキュリティに不安があるサイトは、ユーザーの信頼を損なうだけでなく、集客や問い合わせの機会を逃す原因にもなりかねません。
ここでは、運用保守にかかる具体的な費用項目とその重要性について、事例を交えながら解説します。
1. サーバー・ドメイン費用
ホームページをインターネット上に常時公開し続けるためには、サーバーとドメインの契約が必須です。
この費用は毎月または毎年発生する固定コストとなります。
-
サーバー利用料:月額500円〜3,000円程度(共有・VPS・専用サーバーによる)
-
ドメイン取得・維持費:年間1,000円〜5,000円前後(.comや.jpなど種類によって異なる)
安定性やセキュリティ性能が高いサーバーを選ぶことは、サイトの表示速度や稼働率に大きく影響します。
費用だけでなく、運用体制やサポート内容も含めて選定することが大切です。
2. コンテンツ更新費用
ホームページの内容を常に最新の状態に保つことは、訪問者に信頼感を与えるだけでなく、SEO対策としても有効です。
具体的には、以下のような作業が対象になります。
-
テキストや画像の差し替え
-
新着情報やブログ記事の追加
-
サービス内容の変更・キャンペーン情報の掲載
こうした定期的な更新作業を外注する場合、月額5,000円〜30,000円程度が相場となります。
更新頻度が高いサイトであれば、更新プランをあらかじめ契約しておくことでコスト管理もしやすくなります。
「自社で更新したい」というケースでは、WordPressなどのCMSを導入することで、専門知識がなくても簡単に更新が可能です。
ただし、誤操作によるトラブルもあるため、必要に応じて定期的なバックアップ体制を整えることも検討しましょう。
3. セキュリティ対策費用
ホームページは常に不正アクセスやマルウェアなどの脅威にさらされています。
そのため、以下のようなセキュリティ対策が欠かせません。
-
SSL証明書の導入(HTTPS化)→ 年間0円(無料SSL)〜数万円(企業認証型など)
-
管理画面へのアクセス制限・ログ監視
-
セキュリティプラグイン・ファイアウォール導入
-
CMSの定期アップデート
こうした対策を講じることで、個人情報漏洩やサイト改ざんなどの重大リスクを未然に防ぐことができます。
近年では、実績のある専門業者によるセキュリティ保守契約(月額5,000円〜)も一般的となっています。
▶運用保守費用は“コスト”ではなく“投資”
運用保守にかかる費用は一見「コスト」に見えがちですが、長期的に見れば「サイト価値を維持・向上させるための投資」です。
特に企業サイトや集客を目的としたページでは、運用が成果に直結する重要なフェーズです。
制作実績が豊富な会社では、運用体制もセットで提案してくれるケースも多いため、初期段階での相談がおすすめです。
▶運用保守も含めてホームページは“継続するもの”
ホームページ制作を検討する際は、制作費用だけでなく、その後の運用保守にかかる費用も含めて計画することが大切です。
以下のようなポイントを踏まえ、予算設計を行いましょう。
| 項目 | 相場の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| サーバー・ドメイン費用 | 年間5,000〜30,000円 | 安定性とセキュリティも重視 |
| コンテンツ更新費用 | 月額5,000〜30,000円 | 更新頻度に応じて変動 |
| セキュリティ対策費用 | 年間0円〜数万円 | SSLやプラグイン活用で強化 |
運用体制まで視野に入れておくことが、費用面でも成果面でも成功のカギとなります。
6.ホームページ制作における高額と低額の違い
この章では「高額と低額なホームページ制作の違い」について解説します。
具体的には、高額な制作の特徴とメリット、低額な制作のリスクと注意点といった内容を順にご紹介します。
【6-1】 高額な制作の特徴とメリット
ホームページ制作の費用は幅広く、制作内容や依頼先のレベルによって大きく異なります。中でも「高額」とされる制作プランには、それ相応の理由とメリットがあります。単に価格が高いというだけではなく、企業のビジネス戦略全体を支える重要なツールとしてのホームページを実現できるのが大きな特徴です。
ここでは、高額なホームページ制作に共通する主な特徴と、そのメリットについて詳しくご紹介します。
1. 高品質なデザインと設計
高額なホームページ制作では、プロのデザイナーによる洗練されたビジュアル設計が標準となります。
企業のブランドイメージやターゲット層に応じて、オリジナルのデザインが一から制作されるため、テンプレートにはない独自性と説得力のある印象を与えることが可能です。
また、UI/UX(ユーザーインターフェース/ユーザー体験)設計にも重点が置かれ、訪問者が直感的に操作できる設計となっているため、滞在時間の延長やコンバージョン率の向上にもつながります。見た目の美しさだけでなく、「成果を出すための設計」がなされている点が大きな魅力です。
2. 手厚いサポートとコンサルティング
高額プランでは、制作前からの丁寧なヒアリングや要件整理、企画提案が含まれており、単なる“作業”にとどまりません。
業種や市場特性を理解したうえで、企業の強みをどう伝えるか、何を訴求すべきかを一緒に考えてくれるため、初めてのホームページ制作でも安心して任せることができます。
制作後も、更新や改善提案、効果測定、改善案のフィードバックなどがセットになっているケースが多く、長期的なパートナーとして継続的な支援を受けられるのが強みです。
サポート付きのプランは、専門的な知識がない担当者にとってもおすすめです。
3. SEO対策とマーケティング戦略の実装
高額なホームページ制作には、SEO対策やデジタルマーケティング戦略が組み込まれていることが一般的です。
たとえば、以下のような施策が含まれます。
-
競合分析に基づくキーワード戦略
-
Google検索での上位表示を狙ったコンテンツ設計
-
コンバージョン率を意識した導線とCTA設計
-
広告運用との連携(リスティング・SNS広告など)
これにより、ホームページを単なる情報発信の場から、成果を生み出す営業ツールへと引き上げることが可能になります。
高額な制作費でも、しっかりと成果に結びつける設計がされていれば、投資として十分に価値があります。
まとめ:高額でも成果を実現できる設計とサポートが魅力
高額なホームページ制作は、初期費用が高くなる分、設計・デザイン・運用までトータルで質が高く、成果につながりやすいという特徴があります。
| 項目 | 高額制作での特徴 |
|---|---|
| デザイン | 完全オリジナル・高品質 |
| サポート | コンサル付き・継続支援あり |
| SEO/マーケ戦略 | 広告・集客設計込みで実現 |
コーポレートサイトの刷新や、集客重視のサイト立ち上げ、ブランディング強化など、目的が明確なケースでは高額プランを選ぶ価値は大きくなります。
“費用対効果”を最大化したい場合、戦略的な高額制作を検討するのもおすすめです。
【6-2】 低額な制作のリスクと注意点
ホームページをできるだけ安く作りたいと考えるのは自然なことですが、「安い=お得」とは限らないのがホームページ制作の世界です。
低価格帯の制作サービスには、いくつかの見逃せない注意点やリスクが潜んでいます。
ここでは、低額でのホームページ制作における代表的な問題点と、それを回避するための方法について紹介します。
1. テンプレートの使用とデザインの制約
低価格で制作されるホームページの多くは、既存のテンプレートをベースに構築されます。
そのため、デザインの自由度が低く、他社と似たような外観になってしまうことも少なくありません。
「最低限の情報を載せたいだけ」「とりあえず名刺代わりにサイトを持ちたい」といった用途であれば問題ありませんが、
ブランドイメージや企業の個性を反映させたい場合には不向きです。
また、追加でデザインを変更・修正しようとすると、別途費用が発生するケースも多いため、事前に詳細な仕様の確認が必要です。
2. サポート体制の不足
低額な制作プランでは、サポート体制が簡易的または用意されていない場合がよくあります。
公開後に「画像が表示されない」「メールフォームが動かない」などのトラブルが発生しても、すぐに対応してもらえない、または別料金になるといったケースも。
特に、安価なパッケージサービスでは「納品して終了」というスタンスのところもあり、
運用フェーズでのトラブル解決や更新依頼に対応できないというリスクがあります。
契約前には、どこまでが料金に含まれるのか、どのようなサポートが受けられるのかを確認することが信頼につながります。
3. SEO対策の弱さ
低価格制作では、SEO対策が簡易的または全く考慮されていないケースが多いです。
結果として、検索エンジンで上位に表示されず、集客に結びつかないホームページになってしまうことも。
-
ページ構成が検索エンジン向けに最適化されていない
-
見出しの構造が不適切
-
メタ情報が未設定
-
表示速度やモバイル対応が不十分
これらの「SEOの基礎」が施されていないと、せっかくホームページを作っても、誰にも見られない状態になりかねません。
SEO対策を重視するなら、その知識を持った担当者がいるか、どのような対策が施されるかを事前に確認しておくことが重要です。
まとめ:安く作るなら「安さの理由」を明確に把握しよう
低額なホームページ制作は、初期費用を抑えられる反面、デザイン・サポート・SEOの面で大きな制約があります。
| リスク | 内容 |
|---|---|
| デザイン制限 | テンプレート使用でオリジナリティが乏しい |
| サポート不足 | トラブル対応や更新が別料金・対応外 |
| SEOの弱さ | 表示順位が上がらず集客できない |
「安くても安心して使えるサイトを作るにはどうすればいいか」という視点を持ち、事前にポートフォリオや実績の確認、契約内容の詳細把握を徹底しましょう。
信頼できる業者との連携が、後悔しないホームページ制作につながります。
7.ホームページ制作の際の「費用を抑える」ためのポイント
この章では「費用を抑えるためのポイント」について解説します。
具体的には、費用を抑えるための具体的なコツ、相見積もりの重要性とその方法といった内容を順にご紹介します。
【7-1】 費用を抑えるための具体的なコツ
ホームページ制作にあたって「できるだけ予算を抑えたい」と考える企業や個人事業主は多いものです。
しかし、安く仕上げるためには、どこを抑え、どこにコストをかけるかを明確に見極めることが重要です。
ここでは、実際に制作費を抑えるうえで効果的な3つの具体的な方法をご紹介します。
1. テンプレートの活用でデザイン費を削減
オリジナルデザインにこだわらず、CMS(WordPressなど)で提供されている無料または低価格のテンプレートを活用すれば、デザイン費を大幅に抑えることができます。
すでに整った構成があるため、レイアウトや色味の変更だけで完成度の高いサイトを実現することも可能です。
特に、企業紹介やサービス案内など、構成がシンプルなホームページにはテンプレート利用が向いています。最近では、ビジネス用途に特化したテンプレートも多く、機能性・見た目の両面で十分対応できます。
2. コンテンツは自社で準備する
外注に頼ると費用がかさむのが、テキストや写真、動画などのコンテンツ制作です。これらを自社スタッフで作成することで、コストを抑えることができます。
たとえば以下のような素材を事前にしっかり準備しておくことで、制作会社とのやりとりもスムーズになり、無駄なやり直しの発生も防げます。
-
文章:ライティングノウハウを共有しながら社内で執筆
-
写真:スマートフォンや社内カメラでの撮影でも十分なケースも
-
会社情報や実績紹介:担当者が日常業務の中で収集
3. 必要最低限の機能に絞る
最初からすべての機能を盛り込もうとすると、当然ながら費用はかさんでいきます。
そこで、初期段階では「本当に必要な機能」だけに絞ることが費用を抑えるポイントです。
よく使われる最低限の機能例・お問い合わせフォーム
・サービス紹介ページ
・ブログ/お知らせ機能
・地図・アクセス案内
逆に、予約システム・EC機能・多言語対応などは、必要に応じて後から追加することも可能です。
段階的に拡張できる構成にすることで、初期投資を抑えながら柔軟な運用が実現します。
まとめ:ノウハウを活かし「賢く抑える」ことがポイント
ホームページ制作の費用を抑えるには、「自分たちでできる部分はやる」「必要なことに絞る」「テンプレートをうまく使う」という視点が重要です。
| 方法 | 費用を抑える理由 |
|---|---|
| テンプレート使用 | デザイン工数を大幅削減 |
| コンテンツ自作 | 外注費用をカット |
| 機能の絞り込み | 実装費用を最小限に |
明確な目的を持ち、無理のない範囲で制作することが、最もコストパフォーマンスの高いホームページ制作につながります。
実際に制作に入る前に、社内で対応可能な範囲を洗い出しておくことをおすすめします。
【7-2】 相見積もりの重要性とその方法
ホームページ制作の費用を適正に抑えるためには、複数の制作業者から相見積もりを取ることが非常に重要です。
これにより、費用の相場感を把握できるだけでなく、各社の対応力や提案内容の違いを比較し、最適なパートナーを選定できます。
1.複数業者への依頼で費用と対応力を比較
まずは、3社以上の制作会社やフリーランスに見積もりを依頼しましょう。
その際、ホームページの目的や必要な機能、希望するデザインイメージなど、できるだけ具体的に要望を伝えることが大切です。
同じ条件で依頼することで、見積もり内容の公平な比較が可能になります。
2.見積もり内容の比較でメリットと可能性を見極める
見積もりを比較するときは、単に総額だけを見るのではなく、費用の内訳をしっかり確認することがポイントです。
たとえば、デザイン費、コーディング費、コンテンツ制作費、サーバー・ドメイン費用など、各項目ごとの金額を細かくチェックしましょう。
これにより、どの業者がコストパフォーマンスに優れているか、また必要なサービスをしっかり提供できるかを判断できます。
3.費用以外に知識・実績も加味して判断を
費用だけでなく、制作会社の実績や顧客からの評判、対応の丁寧さも重要な選定基準です。
過去の制作事例を参考に、同じ業種や規模のサイト制作経験があるかを確認しましょう。
また、質問や相談に対して迅速かつ具体的な回答が得られるかどうかも、信頼できる業者選びには欠かせません。
▶まとめ:相見積もりは「時間」と「労力」をかける価値がある
相見積もりは、複数の見積もりを比較するため手間と時間がかかる作業ですが、
その分、費用を抑えるだけでなく、自社に最適な制作パートナーを選べる大きなメリットがあります。
納得できる業者を選ぶために、しっかり準備し、要望や条件を明確にしたうえで相談・比較検討を進めましょう。
8.ホームページ制作の流れと工程
この章では「ホームページ制作の流れと工程」について解説します。
具体的には、ホームページ制作の一般的な流れ、各工程にかかる費用の目安といった内容を順にご紹介します。
【8-1】 ホームページ制作の一般的な流れ
ホームページ制作は、明確な目的設定から始まり、計画的な進行が成果物の質と費用対効果に直結するプロセスです。
ここでは、制作の基本的な流れと、各段階で重要なポイントを紹介します。
1. 企画・要件定義の重要性
まず、ホームページの目的をはっきりと定めることが最も重要です。
ターゲットユーザーは誰か、達成したい目標は何か、どんな機能が必要かなどを洗い出します。
この段階で、競合サイトの分析やキーワード調査を行い、マーケティング視点を取り入れることも効果的です。
企画や要件定義が曖昧なままだと、後の工程で仕様変更や手戻りが発生し、余計なコストや時間がかかる原因になります。
そのため、初期段階で関係者全員の認識をしっかり共有することが成功のカギです。
2. デザイン・設計フェーズの詳細
企画が固まったら、次にワイヤーフレーム(サイトの設計図)を作成し、全体の構成や導線を決定します。
続いて、デザインコンセプトに基づいて、トップページや主要ページのビジュアルデザインを制作します。
このフェーズでは、ユーザーが見やすく使いやすいインターフェース設計を心がけることが重要です。
また、ブランドイメージや目的に合ったカラー・フォント・写真などを選定し、サイト全体の統一感を図ります。
3. 実装・テスト・公開後の運用
デザインが確定したら、HTMLやCSS、JavaScriptを用いてコーディングを行い、実際にWeb上で動作する状態に構築します。
レスポンシブ対応やSEO設定などもここで行われます。
実装後はテスト環境で動作確認を入念に行い、ブラウザやデバイスごとの表示不具合、リンク切れ、フォーム送信の動作などをチェックします。
問題がなければ、本番環境にサイトを公開しますが、制作で終わりではありません。
公開後もアクセス解析を行い、ユーザー行動を把握した上で、改善・更新を継続することが重要です。
また、サーバー管理やセキュリティ対策、コンテンツ更新の保守運用体制も整えておく必要があります。
▶ホームページ制作は、企画・設計・実装・運用の各工程が連携して初めて効果的なサイトが完成します。
特に、初心者でも理解しやすいように、目次や構成をしっかり設定し、管理しやすい仕組みを導入することが成功への近道です。
これらの基本を押さえ、丁寧に進めることで、満足度の高いホームページを効率的に作り上げることができます。
【8-2】 各工程にかかる費用の目安
ホームページ制作の費用は、企画から公開後の運用に至るまで、それぞれの工程で発生するコストの積み重ねです。
ここでは、主な工程ごとに、どのような費用がかかるのか、相場の目安を解説します。
2025年現在、多くの制作会社が公開しているプランを参考に、最新の傾向を踏まえてご紹介します。
1. 企画・設計費用の内訳
ホームページ制作のスタートは、企画・設計フェーズです。ここでは、サイトの目的やターゲットを明確にし、ページ構成や必要な機能を定めます。
-
費用の目安:3万円~20万円程度
※ページ数が多いほど人件費が増加し、コストも上昇します。
この工程には、競合分析、キーワード選定、サイトマップ設計などが含まれ、完成後の成果を左右する重要なステップです。
内容が不明確なまま進めると、後の修正や手戻りが発生し、最大で倍以上の費用がかかる可能性もあるため、事前にしっかりと準備しましょう。
2. デザイン費用の変動要因
次に、サイトの見た目や使いやすさを決定するデザイン費用についてです。
使用する画像の有無、アニメーション表現、修正回数の多さなどが金額に影響します。
-
テンプレート利用:5万円〜10万円前後
-
オリジナルデザイン:15万円〜50万円以上
デザインは企業の第一印象を左右する重要な要素であるため、必要に応じてプロのデザイナーに依頼することをおすすめします。
2025年の傾向としては、スマホファーストのレスポンシブデザインが標準化されており、その対応有無も費用に含まれるかを確認すべきです。
3. コーディング・システム開発費
HTMLやCSSなどによるコーディング作業や、CMS(WordPressなど)を使ったシステム開発費用は、サイトの構造や導入機能によって大きく異なります。
-
静的なHTMLサイト:5万円〜15万円前後
-
CMSサイト構築(WordPress等):20万円〜60万円以上
CMSの導入では、テーマのカスタマイズ、フォーム機能、SEOプラグイン、会員機能などそれぞれの機能追加に応じて費用が加算される点に注意が必要です。
また、コンテンツの作成、写真撮影、動画制作を外注する場合は、別途費用(数万円~数十万円)が発生します。
ホームページ制作の費用は、「何を、どのレベルで、誰に依頼するか」によって変動します。
各工程の相場を把握し、それぞれの作業内容が見積もりにどのように反映されているかを確認することが重要です。
複数のプランを比較しながら、2025年の最新動向や自社の予算に合わせた取捨選択を行い、最適な制作体制を整えましょう。
9. ホームページ制作に関するよくある質問
この章では「ホームページ制作に関するよくある質問」について解説します。
具体的には、自作と外注の比較、ホームページ制作のメリット・デメリットといった内容を順にご紹介します。
【9-1】 自作と外注の比較
ホームページを制作する際、「自社で作成すべきか、それとも外部に依頼すべきか?」という疑問は多くの方が直面するポイントです。
どちらを選ぶかは、予算、時間、スキル、そしてホームページに求める完成度によって大きく異なります。
まず、費用を抑えることを重視するなら自作が有力な選択肢です。
WordPressなどのCMSや、Wix・ペライチなどの無料ホームページ作成サービスを使えば、初期費用をほとんどかけずにサイトを公開できます。
基本的なテンプレートを選び、写真やテキストを入力するだけで比較的簡単に作成が可能です。
ただし、デザインや機能面での自由度は限られており、オリジナル性の高いページ作りには限界がある点に注意が必要です。
一方、制作を外注する場合は費用は高くなるものの、完成度の高いデザインと信頼性のある機能実装が期待できます。
プロの手による設計・ライティング・コーディングにより、ビジネスの目的や顧客に合わせた最適な構成でホームページを作成してもらえます。
また、公開後の運用や改善提案といった継続的なサポートも受けられるのが特徴です。
さらに、自作には制作時間を確保できるかどうかも重要な判断材料となります。
本業と並行してホームページを作るのは思った以上に時間と労力がかかるものです。
十分な時間が確保できない場合や、制作スキルに不安がある場合は、早期に外注を検討するのも賢明な判断です。
最終的には、自社のリソースと目的を総合的に検討し、現時点での最適な選択肢を選ぶことが大切です。
たとえば、立ち上げ初期は自作でスタートし、事業が軌道に乗ってから専門業者にリニューアルを依頼するという段階的な進め方もおすすめです。
【9-2】ホームページ制作のメリット・デメリット
ホームページ制作には多くのメリットがありますが、同時に一定のデメリットも存在します。
自社にとって本当に必要かどうかを判断するためには、両面をしっかり理解することが重要です。
まず、メリットの代表例は「集客効果の向上」です。
適切なSEO対策を施したWebサイトは、検索エンジン経由での流入が期待でき、見込み客の獲得や問い合わせの増加につながります。
ブログ記事や事例紹介などのコンテンツを掲載することで、ユーザーとの接点を増やし、自然検索からのアクセスを促進できます。
また、企業のブランディングを強化できることも大きなメリットです。
コーポレートサイト上に企業の理念や実績、代表のメッセージなどを掲載することで、信頼性や安心感を伝えることができ、競合との差別化にもつながります。
特に、ある程度の規模を持つ企業では、Webサイトの品質がそのまま企業イメージとして認識されるケースも少なくありません。
一方で、デメリットとしては「維持・管理に手間がかかる」点が挙げられます。
公開後も、最新情報の掲載やサービス内容の更新、Webサーバーの保守、セキュリティ対策などが必要になります。
これらは専門知識が求められる場合もあり、社内にWebに詳しいスタッフがいないと対応が難しくなることもあります。
そのため、ホームページを作る際には、「作って終わり」ではなく「運用して活かす」視点を持つことが大切です。
ブログ記事の定期更新やFAQページの整備などを通じて、検索エンジンや訪問者に有益なWebサイトを目指しましょう。
メリットとデメリットを比較したうえで、自社にとって最適なWeb戦略を立てていくことが成功のポイントです。
さいごに:信頼できる“伴走者”と一緒に、納得のいくホームページを。
ここまで、ホームページ制作にかかる費用の相場や、目的別の違い、依頼先ごとの特徴、コストを抑えるポイントなどを詳しくご紹介してきました。
でも、私たち足立区の「町のホームページ屋さん」が一番お伝えしたいのは、ホームページは「いくらかかるか」だけでなく、「誰と、どんな目的で作るか」もとても大切だということです。
高いから安心、安いから不安――それだけで判断するのではなく、
あなたのビジネスや地域活動の想いを“ちゃんと汲み取ってくれる人”と一緒に、
納得できるサイトづくりを進めていくことが、費用対効果の高いホームページにつながります。
私たちは、足立区を拠点に中小企業や個人事業主の方と一緒に、地に足の着いたホームページづくりをしてきました。
「こんな小さなこと、聞いてもいいのかな?」と思うようなご相談も、どうぞ気軽にお問い合わせください。
あなたのビジネスや活動にとって、本当に役立つホームページづくりを、町のホームページ屋として一緒に考えます。
この記事の監修者

中小企業&小規模企業のブランディング&マーケティング総合支援を主事業とした株式会社オプティの代表取締役。特に得意な施策は15年以上の実績を持つSEOによる集客サポート。
『あって相談できる安心』を実現するため「町のホームページ屋さん」を業界初の店舗型として運営。伴走型支援で様々なジャンルの会社をサポートし続けている。
ホームページ制作の補助金のご相談&サポートはお任せください
東京都の北千住の「町のホームページ屋さん」では東京23区や各市町村、東京都や国の助成金や補助金にも幅広く対応しております!
助成金などを使いたいけどよくわからない、どうしていいかわからないなど、各種サポートいたしますのでまずはお気軽にご相談ください。

5万円で高機能ホームページが作れます!
ニュース更新システム&問い合わせフォーム付き。
もちろんスマホ表示完全対応しています!
各区のホームページ補助金にも完全対応しております!
【町のホームページ屋さんの特徴」
実店舗だから「顔が見える」安心のWEB制作を実現。
お客様に寄り添う業界初の店舗型運営。
だからWEBなどが苦手なお客様にも安心と安全をご提供いたします。
「会って相談できる安心。顔が見える安心。」
無料相談はいつでも何度でも受け付けております。
どうぞお気軽にご来店くださいませ。